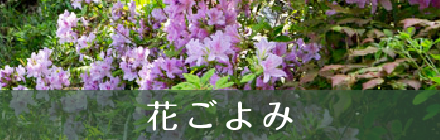日中は半袖で過ごせるほどの気温になりました。このゴールデンウィークも多くのお客様にお越しいただき、ありがとうございました。公園スタッフも園内巡回時や水景園受付、イベント開催時等でお客様がそれぞれにお楽しみいただいている様子を感じられ、嬉しく思っている次第です。芝生広場ではご家族連れが遊具で遊ばれたり、ピクニック、お散歩、虫捕り、運動を満喫する方々の姿を見受けられました。
さて、この芝生広場の遊具があるエリア付近には、夏場になるとその丈2mに届きそうなほどに成長するフトイと共に濃紫の花弁が美しいアヤメが花を付けています。今回は雨のローケーションにも一層映えるアヤメ科植物に関する「よろず話」を紹介します。
●アヤメ/Iris sanguinea Hornem 中国名:溪蓀、韓国名:붓꽃
・・・アヤメ科アヤメ属の多年草。垂直に伸びた茎の先端に蕾を数輪つけ、順次開花していきます。株分けをしても生育旺盛で、多数の株立ちとなります。日本のほか朝鮮半島や台湾、中国が原産の植物です。
園内のアヤメは遊具付近の小川近くにあることから、これからの季節は子ども達の視界にも入る場合も多いようです。観察をされる際は、花を折らないようにしてくださいね。また、雨天後などは地面が緩くなっていることも…汚れても良い靴でお越しください。
このアヤメの他、園内のアヤメ科植物は、カキツバタやキショウブ、ハナショウブ、竹林のもとに繁茂するシャガなどを植栽しています。単子葉植物の類で、花弁が放射相称または左右対称、外側、内側の花弁(外花被、内花被)が3枚ずつあり、3本のおしべがあることなどの特徴が挙げられます。また、これらの開花シーズンとは異なり、春先に開花するクロッカスやフリージアもアヤメ科の仲間です。

●カキツバタ/Iris laevigata Fisch 中国名:燕子花、韓国名:제비붓꽃
・・・アヤメ科アヤメ属の多年草。日本、朝鮮半島~東シベリアが原産で、アヤメと比較し、花茎は垂直には成長せず湾曲を見せます。花は茎先端に数輪の蕾を付け、順次開花。花弁の付け根に白く尖った模様のあることが特徴です。園内では、水景園の山棚田に群生するエリアがあり、ゴールデンウィーク期間中には既に多くの開花が確認できました。水景園でカキツバタが植えられた場所をスタッフの間では「八ツ橋」と表現しています。
カキツバタに八ツ橋…皆さんの頭には平安時代の歌人や、かの有名な屏風が浮かんだのではないでしょうか。まずは平安時代の歌人を代表する在原業平。「からころも きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびしぞおもふ」愛する人と別れて都を離れる決意をし、東下りをする道中にあったのがカキツバタの名所でした。現在の愛知県知立市に位置すると言われています。この歌には『伊勢物語』の主人公の心情が如実に表れており、その遍歴の一端が感じられます。一方で、屏風を連想された方は、東京・根津美術館蔵の国宝『燕子花図』のデザイン性や豊かな色彩を思われたのではないでしょうか。これは18世紀に尾形光琳が紙本金地着色で仕上げた六曲一双の屏風で、縦151.2cm、横358.8cmのサイズです。
平安時代の歌人・在原業平が伊勢物語のなかで、か・き・つ・ば・たの文字を句頭に入れて歌を詠んだ往古から、江戸時代を代表する絵師の作品、そして現代に至るまで、八橋(八ッ橋)は美しいカキツバタの咲き誇る場所であったのです。

●キショウブ/Iris pseudacorus L 韓国名:노랑꽃창포
・・・アヤメ科アヤメ属の多年草。アヤメやカキツバタよりも背丈が高く、葉表面の凹凸も深いです。遠くからでも発見できる鮮黄色の花を付けます。明治時代にヨーロッパから導入され、日本各地に広まりました。こちらもかなり強い繁殖力を持ち、在来種の生育する環境を脅かす対象として、日本の侵略的外来種ワースト100にも選定されています。公園では生物多様性の観点から逸出しないようにコントロールを行いながら、共存の選択を取り、その鮮やかな花姿をご覧いただいています。

●ハナショウブ/Iris ensata Thunb. var. ensata 中国名:日本鸢尾
・・・アヤメ科 アヤメ属の多年草。日本、朝鮮半島~東シベリアが原産で、日本国内では江戸時代以降園芸種の改良が進み、地域ごとに特色ある品種が多く生み出されました。その代表的な例が、花色・花姿共に変化に富む江戸系、外側の花弁(外花被)が3枚の品種が多く、花弁が垂れる特徴のある伊勢系、ボリューム感があり、外花被が6枚の品種が多い肥後系です。なお、端午の節句でショウブ湯に利用されるのは、サトイモ科のショウブであり、ハナショウブとは別の植物です。

今回は、アヤメ科植物のおはなしでした。これからの季節に見ごろを迎えるこれらの植物。ぜひけいはんな記念公園でお楽しみください。